今回は、読みだしたら止まらないおすすめの面白い日本の歴史漫画を「歴史順」に紹介しています。
できるだけ古代から現代までの歴史を通して見直せるように配置を厳選しましたので、大人の学び直しにもピッタリです。
時代ごとに読むもよし、興味のある時代をピックアップして読むもよし。ぜひ、日本史の旅を楽しんでください。
日本の歴史漫画おすすめ作品【弥生時代~飛鳥時代】
まずは、日本が生まれ、国が形作られていく様を魅力的なストーリーで表現したおすすめ漫画を紹介します。
『火の鳥』
手塚治虫先生の『火の鳥』は、伝説の不死鳥をめぐる物語です。
『火の鳥』は日本だけでなく、海外の歴史に題材をとったストーリーもあり、また過去だけでなく未来を描いたSF的な物語も展開されます。

今回は本記事のテーマに合わせて、日本の歴史を追えるものをピックアップしていますが、もしシリーズに興味が出てきたなら、他の『火の鳥』作品もぜひ読んでみてくださいね。
火の鳥・黎明編
『火の鳥・黎明編』は、日本史の初期時代を舞台に、不死鳥と永遠の命をめぐる壮大な物語が繰り広げられる歴史漫画です。本編は長編漫画、火の鳥シリーズの最初の作品でもあります。
主人公は、クマソの少年ナギ。クマソを滅ぼしたヤマタイ国の武人猿田彦との奇妙な共同生活からいつしか家族愛が芽生えていくのですが、やがてヤマタイ国と大陸の戦争にまきこまれていきます。
スサノオ、ニニギなど日本神話の登場人物と、邪馬台国、クマソなどの日本史にも登場する国が混じりあい、壮大な人間ドラマが展開されます。
手塚治虫先生の漫画は、難解なテーマを扱いつつも、ストーリーは堅苦しくなく、歴史の予備知識がない人でもすらすらよめるのが特徴です。古代日本史や日本神話への興味をかきたててくれる歴史漫画の最初の一冊としておすすめです。
火の鳥・ヤマト編
同じく火の鳥シリーズのヤマト編では、ヤマタイ国が滅び、ヤマトの国が力を持った時代の話が描かれています。
ヤマトの王子、オグナは、殉死制度に反対する先進的な考え方の持ち主です。クマソ征伐を命じられるのですが、クマソの党首川上タケルは立派な人物だと分かり、さらにその妹にも惹かれるようになります。
火の鳥の中では、短くまとまっている話ではありますが、オグナの心の葛藤は見ていて苦しくなるほどです。また、ネタバレになるので控えますが、権力に対抗する力なき者たちの最後の展開も凄まじいインパクトがあります。

人はどう生きたらよいのか、不老不死を越える幸せとはなにかを見いだせるおすすめの歴史漫画です。
『火の鳥シリーズ』には、他にも日本史の勉強になるストーリーがたくさんありますよ!
・鳳凰編…奈良時代の仏師を主人公にした物語。
・乱世編…平安時代末期の源平合戦が舞台になる物語。
・太陽編…飛鳥時代の白村江の戦いと壬申の乱をテーマとした物語。
『日出処の天子』
『日出処の天子』は、厩戸皇子(聖徳太子)を一種の超能力者として扱った歴史漫画です。
この作品では、朝廷で勢いを増している蘇我氏の若き後継者、毛人(えみし)の視点を中心に、天才少年、厩戸皇子の葛藤が描かれます。
厩戸皇子は、10歳のころから大人顔負けの知識を持ちながら、女性と見まがうほどの美貌、さらには、人ならざるものを見たり、操ったりする能力すらも兼ね備えていました。
やがて皇子は朝廷の権力争いの中で、豪族たちや天皇すらも操る力を持ち始めますが、心の中にあるのは異能ゆえに母に受け入れられず、家族から孤立している孤独感です。皇子の異能の力を覗き見た毛人は、自皇子に惹かれ、また、皇子も唯一自分の世界を共有できる毛人に強い執着を覚えていきます。
この飛鳥時代は、同族同士での婚姻関係を結び、一族の力を増すことが当たり前だった時代です。そのため、天皇家と豪族の家系図は頭が痛くなるぐらい複雑なのですが、物語を読む中で何度も登場する家系図を見、各キャラクター達に感情移入するうち、だんだんと人物像が頭に入ってくるから不思議です。
この漫画を読めば、蘇我馬子と蘇我蝦夷、どっちが親でどっちが子だっけ?と迷うことはなくなるはず。
愛憎絡み合うドロドロの人間関係に没頭しながら、古代日本史の知識が身につく稀有な漫画、発表年代は古いですが、令和の今読んでも夢中になれるはずですよ。

【個人的感想】毛人は別に悪いことしてないけど、だいたいこのとは毛人のせいなんですよね…。
日本の歴史漫画おすすめ作品【奈良時代~平安時代】
続いて紹介するのは、奈良時代から平安時代をテーマにした歴史漫画2作品です。
飛鳥時代から見られた天皇家、そして貴族どうしの争いがより激しくなり、さらに仏教が権力を持つようになった時代のパワーゲームに注目です。
『阿・吽』
『阿・吽』は、同時代に生まれた天才僧侶、最澄と空海が主人公の濃厚な歴史漫画です。
将来を期待されたエリート、最澄は純粋な心を持ち世を救おうとする青年。国分寺での仏教界の腐敗を目にし、山に入って自分の仏教の道を探ろうとします。
一方、自身の身を壊すほどの知識欲にあふれた少年・真魚(のちの空海)は、不思議な僧侶・勤操と出会い、仏教に傾倒していきます。

この歴史漫画では、最澄と空海についてはもちろん、奈良末期から平安初期までの政治背景についても丁寧に書かれています。
例えば、平安京遷都までのごたごたや、桓武天皇死去後の政治的な混乱、藤原家内の権力争いはこの作品を読むと理解が進みます。「奈良や平安は重要人物が多すぎて、誰が誰だかわからない!」と教科書を投げた人にとっては大変ありがたいおすすめの歴史漫画です。
特に「薬子の変」での藤原式家の没落と藤原北家が台頭する描写には注目です(次に紹介する『応天の門』では、この北家が中心となり、政治を意のままにしていることが分かります)。
また『阿・吽』は、仏教の内容を美麗な絵で芸術的に表現している点が特徴的です。
歴史のみならず、仏教にも興味がわく知的好奇心をくすぐる歴史漫画ですよ!

【個人的感想】どんどん生き生きしていく空海に対して、最澄が不憫すぎる…。
『応天の門』
『応天の門』は、平安時代の有名人菅原道真と在原業平がコンビを組んで事件を解決していくミステリー調の歴史漫画です。
平安の都で起きる謎の女官失踪事件、鬼の仕業とも噂されるこの事件を調査していた在原業平は、頭脳明晰な学者の卵、菅原道真と出会います。これを機に、事件が起きるたび、業平は道真を頼って真相を究明しようとするのですが…。
『応天の門』は、時代的には『阿・吽』より少しあとのお話。藤原北家が力を持ち、藤原良房から基経に権力が移り変わるぐらいの時期の話です。
ミステリーやサスペンスが主軸になっている話ではありますが、毎回起こる事件が横軸とすると、縦軸として機能しているのが藤原家の権力争いにまつわるストーリーです。
各事件は道真の知識によって、毎回解決を見るものの、藤原に関するところだけはぼかされており、後々の大きな事件への伏線になっているようなところがあります。
承和の変など、日本史における大事件が題材になっている話もあり、日本史に興味を持つきっかけづくりにぴったりの歴史漫画です。

なお、業平が藤原家の姫・高子と駆け落ちしたという『伊勢物語』の話もしっかり漫画の中に登場します。古典好きにもおすすめの歴史漫画です。
日本の歴史漫画おすすめ作品【鎌倉時代~南北朝時代】
『アンゴルモア 元寇合戦記』
『アンゴルモア 元寇合戦記』は、元寇を扱った珍しい歴史漫画です。
時は1274年、元御家人の朽井迅三郎(くちいじんざぶろう)を含む流刑囚達は、来たる元からの襲撃に備える兵士として最前線の対馬に送られます。
圧倒的多数で襲ってくる元に対して、対馬の兵はごくわずか。九州より援軍を送るという少弐景資(しょうにかげすけ)の言葉を信じ、対馬での防衛戦が始まります。
主人公の朽井は、鎌倉幕府内の権力争いに巻き込まれて、流刑囚となっていますが、義経流の使い手で凄腕の武士。最初こそ、見知らぬ土地での戦にやる気を見せなかったものの、次第に鎌倉で失った生活と対馬を重ねるように。冷たく見えた性格も徐々に熱を帯び、対馬の民との信頼関係が築かれていきます。
歴史上、元にとっての対馬戦が博多上陸のための前哨戦であり、対馬側が圧倒的な負け戦だったことは揺るぎません。だからこそ、登場人物たちは「勝つこと」ではなく、「一人でも生き残る」ことを目指して奮闘します。
大軍に対しての防衛線ということで、人はどんどん死にますし、昔の戦ゆえのグロテスクさが際立つ作品ではありますが、人が自分たちの生活を必死に守ろうとする泥臭さがこの作品の魅力でもあります。
また、元の内情について触れている部分もあり、一枚岩でない「多国籍軍の集合体」としての元寇に気づかされるところも面白いです。

読んでいると「一所懸命」のキャッチフレーズが頭から離れなくなるはず。
なお、対馬編後の続編を描いた『アンゴルモア 博多編』も発表されていますよ。
『逃げ上手の若君』
『逃げ上手の若君』は、日本史の中で埋もれがちな「中先代の乱」(北条時行が起こした反乱)をメインテーマに据えた歴史漫画です。
主人公は、鎌倉将軍家の跡継ぎでありながら、武芸嫌いで逃げることが大好きな北条時行(ほうじょうときゆき)。鎌倉幕府を滅ぼした足利尊氏と戦うため、信濃国の神官・諏訪頼重(すわよりしげ)と手を組み、前代未聞の「逃げて勝つ」戦を仕掛けていきます。
この歴史漫画は『魔人探偵脳噛ネウロ』『暗殺教室』でヒットを連発している松井優征先生の第三作。松井作品らしく、戦って死ぬことが誉の時代を舞台に「逃げて生きる」ことを大事にした主人公の活躍を描くというひねった設定がたまりません。
宿敵・足利尊氏をはじめ、癖の強いキャラクターがこれでもかと登場し、現代的なたとえも多用されているため、ややこしい時代背景を楽しく眺められます。
鎌倉幕府滅亡から建武の申請を経て、足利家の内紛に至るまでの様子がしっかり描かれており、南北朝時代がややこしすぎて日本史が嫌になったという人はぜひご一読をおすすめしたい歴史漫画です。

なお、本作には胡散臭い神官の諏訪頼重や、敵の小笠原貞宗など、魅力的なおっさんが多数登場します!推しのおっさんを、ぜひ見つけてください。
日本の歴史漫画おすすめ作品【安土桃山時代~江戸時代】
安土桃山時代のダイナミックな戦闘を経て、世は徳川が収める太平の世江戸時代へと移り変わります。しかし、一見平和な江戸時代でも、その中では激しい権力争いが繰り広げられていました。
ここからは、武士の世界が垣間見える三つの歴史漫画をご紹介します。
『九国のジュウシ』
『九国のジュウシ』は、安土桃山時代に九州で行われた激しい戦闘「岩屋城の戦い」を舞台とした歴史漫画です。
物語は、大友家家臣・高橋紹運(たかはしじょううん)は、狼の母に育てられた子供・十四郎(じゅうしろう)と出会うところから始まります。弱った母に食事を与えるため、戦場で死体を集める十四郎の並外れた強さに魅了された紹運。彼は十四郎を自軍に迎え入れようとします。
「岩屋城の戦い」では、5万人の島津軍と800人にも届かない数の高橋軍がぶつかりました。本作は、圧倒的劣勢にもかかわらず、2週間の間耐え抜いた高橋軍にスポットを当てた意欲作です。

独自の死生観をもつ十四郎の存在は、なかなか考えさせられるものがあります。
また達観しているように見えた彼の中の人間らしい部分が徐々に見えてくるところにも注目です。
なお、高橋家の存在は知らないという人でも、戦国最強と名高い立花宗茂(たちばなむねしげ)の名前は聞いたことがあるのではないでしょうか。実は、高橋紹運は宗茂の実の父です。
本作では、立花道雪の家に婿養子に入る前の若い宗茂の姿も登場します。立花誾千代(立花道雪の娘)と宗茂の初々しいエピソードも必見のおすすめ歴史漫画です。
『へうげもの』
『へうげもの』は、茶人として名高い戦国大名・古田織部(ふるたおりべ)を主人公にした歴史漫画です。
織田信長が天下に手を掛けたころ、その家臣である古田左介(ふるたさすけ)は、茶器への物欲と武人としての出世のはざまで悩んでいました。やがて本能寺の変が起こり、時代は豊臣に傾いていきます。古田は、信長の時代から豊臣全盛期を経て、徳川の世が来るまでの怒涛の時代を、戦と文化の両面から時にシリアスに、時にコメディ満載で乗り切っていきます。

本作で注目すべきは、歴史の流れの中心に茶道と数寄文化を据えたことです。
歴史上の重要なターニングポイントでキーアイテムとして活躍するのが、古田が魅了された茶器の数々です。敵を懐柔するために、味方の結束を高めるために、たくさんの名器が登場します。本作では名器を形容するオノマトペが非常に独特で秀逸!ぜひ作品内で確かめてほしいです。
また、本作には伊達政宗や細川忠興などの戦国武将はもちろん、俵屋宗達、出雲阿国など、この時代に活躍した文化人が多数登場し、作品を彩ります。
とはいえ、内容はけして難しくなく、むしろギャクより。
主人公の古田織部は、手癖が悪く、物欲に支配された俗物で、めちゃくちゃ人間臭く描かれています(にもかかわらず、時々すごくかっこいいのですが)。
サブタイトルもファンキーなものですし、秀吉死亡の大事なシーンでもまさかの「あの歌」が流れるというびっくりの演出が。
作者が良い意味で遊んでいることが分かる「堅苦しくないのに歴史と文化が学べてしまう」不思議な作品になっています(あくまでフィクションなので本筋の歴史と混同しないようにだけは注意!ですが)。
本作を貫く「人生には笑いが大事」というテーマ感もとても良いですよ!
なお、本作後半では「大坂の陣」の様子がかなり詳しく描かれています。漫画ではありませんが、『幸村を討て』を併読するとより一層楽しめると思います。
歴史漫画『へうげもの』に魅了された人には、次の博物館もおすすめですよ。
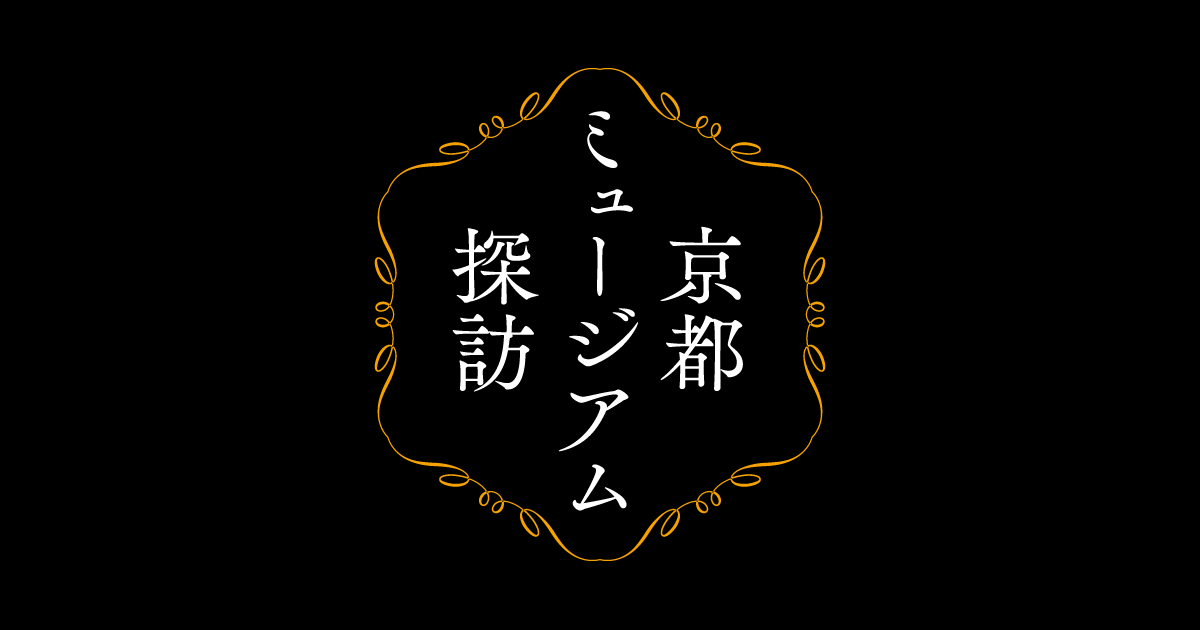
『大奥』
『大奥』は、男女逆転したIFの江戸時代をドラマティックかつ繊細に描いた歴史漫画です。
徳川家光の時代に流行った謎の病、赤面疱瘡によって日本の男性の数は激変。家光も病により死亡し、その血を引く姫が女性将軍の地位に就くことに。
本来は女性の園であった大奥は、女性将軍のために男性を集める場所へと変化していくことになります。
歴代の徳川将軍や田沼意次、松平定信ら幕府の重鎮を女性として描きながらも、政策や事件は歴史上の内容に沿って矛盾なく進んでいきます。また、江戸幕府の歴史とともに謎の病との戦いもしっかり描かれているというストーリーテーリングのうまさ。
家光から慶喜まで、江戸幕府の歴史を丸々詰め込んだ濃厚な内容なのですが、しかもその一つ一つのエピソードが面白く、読む手が止まらない名作です。読み終えたころには、歴代徳川将軍の名前が言えるようになっていた、という読者も少なくないはずです。
さらには各将軍と大奥の男性たちの切ない恋や、「女性」が表舞台で活躍することの壁、「女性」としての役割を強要されるつらさなど、ジェンダー問題を投げかけるテーマ性も魅力の一つです。

徳川将軍の名前が丸暗記できなかった人にはぜひおすすめしたい歴史漫画です!
日本の歴史漫画おすすめ作品【明治時代】
江戸幕府が倒れると、海外に開かれた新しい時代がやってきます。
しかし明治は、旧時代の名残りによる軋轢があちこちで生じる怒涛の時代でもありました。
そんな明治の香り漂う二つのおすすめ歴史漫画を紹介します。
『るろうに剣心 -明治剣客浪漫譚-』
『るろうに剣心 -明治剣客浪漫譚-』は、明治時代を舞台に逆刃刀を持った流浪人・剣心の活躍を描いたバトル歴史漫画です。
明治時代、父から受け継いだ剣術道場を守ろうと奮闘する少女、神谷薫(かみやかおる)の前に現れたのは、人を殺せない逆刃刀(さかばとう)を持った流浪人・緋村剣心(ひむらけんしん)。優男にみえる彼ですが、実は幕末に維新志士「人斬り抜刀斎」として暗躍した過去を持っていました。

人を斬らずに生き抜こうとする元人斬りの生き様を描き切った名作です。
『るろうに剣心』は、飛天御剣流という秘伝の剣術を中心とした迫力あるバトルが魅力ですが、明治という激動の時代に絡んだ歴史的な話が随所に挟まれているところにもおもしろさがあります。
例えば、作中には新選組やお庭番集他、明治維新の立役者「山県有朋」や「大久保利通」が登場します(大久保暗殺の背景については、本作ではかなり大胆にアレンジされています)。
また、廃刀令や廃仏毀釈(はいぶつきしゃく)など歴史的な出来事が物語の重要なポイントになっていることも多いです。
明治の時代に関心を持つための、よいきっかけになることは間違いないでしょう!
漫画のおまけについているキャラクター創作秘話も、なかなか興味深いですよ。
『ニュクスの角灯』
『ニュクスの角灯』は、海外と日本のアンティークの知識が随所に織り込まれている明治ドラマです。
舞台は1878年の長崎。西南戦争で父を亡くした少女、美世(みよ)は、海外の珍しい品を扱うアンティーク店「「蠻(ばん)」で働くことになります。
本作は自分に自信がなかった美世が海外の文化に触れ、成長していく様を追った成長譚です。一方で途中からは店の店主百年(ももとし)のパリにおける恋愛事情についても話が進みます。
序盤は美世の視点で、中盤は百年の視点で、後半は両者の視点で明治における日本と海外の文化、アンティークを基軸とした人間模様が万華鏡のように描き出されます。特に百年がパリに行った後の人間臭い展開にはぐいぐい引き込まれました。

「ニュクスの角灯」というタイトルが回収された一コマは、特に圧巻。全6巻とは思えないほどの内容の濃さです。
また本作は、明治時代における歴史的な文化のさりげない織り込みが大変見事です。フィクションながら、実在した人物や当時の文化がうまく物語の中に溶け込んでいて、一話ごとに丁寧なコラムも付いています。明治時代の文化的香りを存分に味わえるおすすめの歴史漫画といえるでしょう。
なお物語は1944年の熊本、空襲を避け防空壕に隠れていた美世が孫に自身の少女時代を語り始めるところからスタートします。実は、このスタートがこの物語にとって大きな意味を持っています。

賛否両論となったラストシーンは、ぜひ自身の目で確かめてください(私はコミックス最終巻のコラム込みで素晴らしい構成だと思いました)。
日本の歴史漫画おすすめ作品【大正時代~昭和】
最後に紹介するのは、今から少し昔の大正と昭和の物語。
現代と未来を考えるために重要なポイントとなるこの二つの時代を理解するために、おすすめの歴史漫画を紹介します。
『昭和天皇物語』
『昭和天皇物語』は、大正と昭和という激動の時代を物語形式で振り返るのにとても適しているおすすめ歴史漫画です。
タイトルの通り、主人公となるのは、のちの昭和天皇である裕仁(ひろひと)。
物語は純粋で孤独な裕仁の少年時代からスタートします。心を許した養育掛・タカとの別れ、海外への留学、結婚を経て、戦争に向かっていく時代に天皇に即位する、怒涛の人生が漫画の中に展開されています。
漫画を読んでいると日本の最高峰にいるはずの「天皇」という地位が、いかにままならないものかを思い知らされます。日に日に増大する軍部は、天皇親政を歌いながら、裕仁の言葉を聞き入れようとしません。

昭和という時代がどのように転がり落ちていったのかがよくわかる構成になっており、また、天皇という立場の苦悩もしっかり描かれている名作です。
昭和は、背景事情が複雑な血なまぐさい事件が連発し、首相もどんどん入れ替わる時代です。教科書を読んでいてもよくわからなかったり、人物名が覚えられなかったりして、近代史に苦手意識を持つ人も多いでしょう。しかし、漫画を読んだ後は「原敬と犬養毅、どっちが先に首相になったのか」など、日本史の問題にすらすら答えることができるようになっているはず。
ただし、漫画では重要人物がさらっと出てきて、さらっと退場していくところもあるので、歴史全体の流れを押さえつつ読みたいという人は、後述する『新もう一度読む山川日本史』などの参考書と併読するとより分かりやすいでしょう。
『ペリリュー -楽園のゲルニカ-』
『ペリリュー』は、太平洋戦争中に激しい戦闘が行われた「ペリリューの戦い」を描いた歴史漫画です。
主人公は漫画家を目指す普通の青年、田丸一等兵です。送り込まれた戦場は、サンゴ礁が美しい南の島、ペリリュー島でした。この美しい島と戦争が結びつかない彼ですが、やがて激しい戦闘が始まります。
田丸と同じ年齢ながらリーダー的気質で周りを引っ張っていく吉敷上等兵、頼りになる島田上等兵らと戦闘を潜り抜けていく田丸でしたが、戦局はどんどん悪化していきます。
武田一義先生の絵は丸っこくて可愛らしいので、一瞬これで激しい戦場が描けるのかと疑ってしまうかもしれません。しかし、読みだすとこの絵だからこそ戦場の残酷さが一層際立ってくるのが分かります。
『昭和天皇物語』が、指導者の目線から描かれた昭和であるなら、『ペリリュー』は底辺から見た昭和です。それゆえに、感情移入して読めてしまい、いっそうつらくなるのですが、ストーリー構成が非常に見事なので、「しんどいけど続きが気になる」とぐいぐい読んでしまいます。

キャラクターの個性付けもしっかりしています。フィクションではありますが、だれがどのように生きたのかをしっかり見届けてほしいと思います。
『アドルフに告ぐ』
最後に紹介するおすすめ歴史漫画は、ヒトラーの秘密に迫る濃厚なヒューマンドラマ、『アドルフに告ぐ』です。
この漫画は、三人のアドルフを軸として展開する物語です。一人は、神戸に赴任中のドイツ人外交官の息子、アドルフ・カウフマン。その親友でユダヤ人のパン屋の息子アドルフ・カミル。最後の一人は、あのアドルフ・ヒトラーです。
物語の語り手となるのは、ベルリンオリンピックの取材でドイツを訪れていた記者の峠草平という日本人です。彼は弟の死にアドルフ・ヒトラーの重大な秘密がかかわっていることを知ってしまい、ゲシュタポに追われることに。一方、神戸に住む二人のアドルフも意図せずにこの秘密を知ってしまいます。
第二次世界大戦と戦後を舞台として、日本とドイツをまたぐサスペンス描写に読む手が止まらなくなる本作。ベルリンオリンピックやゾルゲ事件などの歴史的事実とフィクションが巧妙に織り交ざった名作です。読めば日本史だけでなく、海外の事情も頭に入ってくるのではないでしょうか。
とはいえ、戦争で徐々に狂っていくカウフマン少年の倫理観には、思わず目をそむけたくなる時もあります。
とくに本作のラストは、現代の戦争につながる印象深いシーンで終わり、胸がずんと重くなるはず。今、手塚先生が生きていたら現状をどれだけ嘆くでしょうか…。

冒頭で紹介した『火の鳥』も最後に紹介した『アドルフに告ぐ』も、手塚治虫先生の歴史漫画です。手塚作品を読んでいるだけでも、かなり歴史の勉強になりますね。
日本の歴史漫画のおともに使いたい参考書
ここまでおすすめの歴史漫画を紹介してきましたが、歴史漫画はあくまでフィクション。実在しない登場人物や事件が起こることもありますし、ストーリーの都合上、細かい歴史背景は語られず「知っている前提」で話が進むこともあります。
そんなときの道しるべとなるのが日本史の参考書です。大人向けのやり直し日本史として描かれている参考書はいくつかありますが、私のおすすめは『もう一度読む山川日本史』シリーズです。
こちらのシリーズでは、歴史の重要語がしっかり解説されており、資料も豊富に掲載されています。

特にうれしいのが家系図が充実しているところです。
例えば、『阿・吽』や『応天の門』を読んでいて、藤原家と天皇家の婚姻関係がいまいちわからないという人にとって、山川日本史に載っている「皇室と藤原氏の関係系図」は大いに役立つでしょう。
また、『日出処の天子』では、任那というキーワードが登場しますが、こちらも山川日本史で調べると日本にとってどれだけ重要なものだったかがよくわかるはず。
『昭和天皇物語』で激しく入れ替わる首相と時代背景についても、この参考書で全体的な流れを押さえておくと読みやすくなるでしょう。

個人的には『へうげもの』の古田織部や織田有楽斎に触れている箇所があったのがうれしかったです。
まとめ
「おすすめの日本の歴史漫画」、いかがだったでしょうか。興味のある作品が見つかりましたか?

しかし、今回の記事を書いていて、歴史というのは権力争いと戦争の繰り返しなんだなとつくづく思いましたね。争いを描いていない歴史漫画はないのではないかと思ったほど…。

その中でも、平和や理想を求めて諦めない登場人物たちの姿はまぶしかったです。
学生時代、歴史の授業が苦手だったという人は、歴史を暗記するだけのものととらえていたのかもしれませんね。
しかし、歴史というのは人の営みの集大成。じっくり見れば、過去を生きた人たちのダイナミックでドラマティックな世界は、とても面白いものです。
そんな歴史を題材にした漫画は、迫力満点。登場人物たちが力強く過去を生きる様には、きっと引き込まれてしまうはず。そして、読み終わったころには、教科書をいくら読んでも頭に入ってこなかった人物名、歴史名をあっさり覚えていることに驚くのではないでしょうか。
ここで紹介しているおすすめ歴史漫画をきっかけに、少しでも歴史好きの人が増えてくれたらうれしいです!
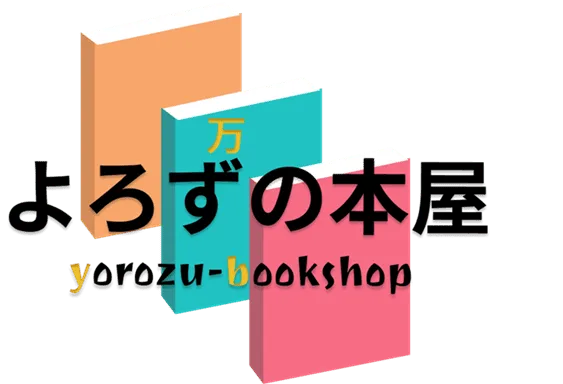
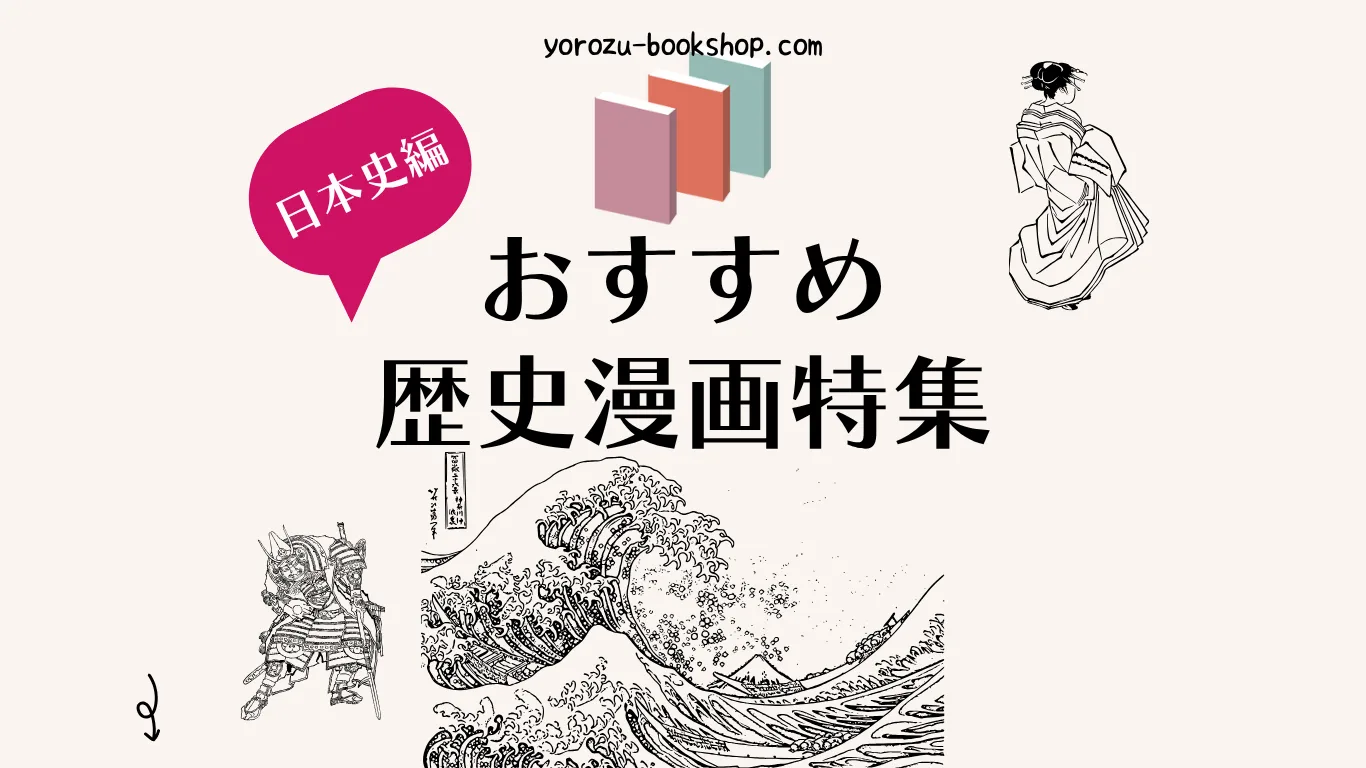
![火の鳥(1(黎明編)) [ 手塚治虫 ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/0227/9784022140227.jpg?_ex=128x128)
![火の鳥(3(ヤマト編・宇宙編)) [ 手塚治虫 ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/0241/9784022140241.jpg?_ex=128x128)
![日出処の天子 完全版 1 [ 山岸 凉子 ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/2648/9784040682648.jpg?_ex=128x128)
![阿・吽 1 (ビッグ コミックス) [ おかざき 真里 ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/7124/9784091867124.jpg?_ex=128x128)
![応天の門(1) (バンチコミックス) [ 灰原薬 ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/7429/9784107717429.jpg?_ex=128x128)
![伊勢物語 (河出文庫 古典新訳コレクション) [ 川上 弘美 ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/9992/9784309419992_1_3.jpg?_ex=128x128)
![アンゴルモア 元寇合戦記 第1巻 (角川コミックス・エース) [ たかぎ 七彦 ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/7837/9784041027837.jpg?_ex=128x128)
![アンゴルモア 元寇合戦記 博多編 (1) (角川コミックス・エース) [ たかぎ 七彦 ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/4892/9784041084892_1_3.jpg?_ex=128x128)
![逃げ上手の若君 1 (ジャンプコミックス) [ 松井 優征 ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/7100/9784088827100_1_2.jpg?_ex=128x128)
![九国のジュウシ 第1巻 (ハルタコミックス) [ 西 公平 ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/1003/9784047361003.jpg?_ex=128x128)
![へうげもの(1)【電子書籍】[ 山田芳裕 ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/rakutenkobo-ebooks/cabinet/1820/2000000231820.jpg?_ex=128x128)
![幸村を討て (中公文庫 い143-2) [ 今村翔吾 ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/5795/9784122075795_1_20.jpg?_ex=128x128)
![大奥 1 (ジェッツコミックス) [ よしながふみ ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/3017/9784592143017.jpg?_ex=128x128)
![るろうに剣心 1 (ジャンプコミックス) [ 和月 伸宏 ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/4998/9784088714998_1_3.jpg?_ex=128x128)
![ニュクスの角灯(1) (SPコミックス) [ 高浜寛 ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/4210/9784845844210.jpg?_ex=128x128)
![昭和天皇物語(1) (ビッグ コミックス) [ 能條 純一 ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/7176/9784091897176_1_17.jpg?_ex=128x128)
![ペリリュー ─楽園のゲルニカ─ 1 (ヤングアニマルコミックス) [ 武田一義 ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/1877/9784592141877.jpg?_ex=128x128)
![アドルフに告ぐ(1) (手塚治虫文庫全集) [ 手塚 治虫 ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/7707/9784063737707.jpg?_ex=128x128)
![新 もういちど読む山川日本史 [ 五味文彦 ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/0908/9784634590908_1_3.jpg?_ex=128x128)

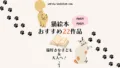
コメント